40代はもう若くはない? 〜アラフォー世代は何故年寄り扱いされるのか?〜
 |
| Malachi WittによるPixabayからの画像 |
はじめに
かつて、企業内では今でいうアラフォー世代は年寄り扱いされる時代がありました。
1980年代初頭の日本は、かつての高度経済成長の勢いは完全に衰えていましたが、極端なドル高のおかげで対米輸出は絶好調でした。しかしご存知の「プラザ合意」以降状況は一転し、円高不況の波が社会全体に広がり始めて、輸出関連の企業は打撃を受け、中小の企業では倒産が相次いだのでした。そのため製造を主とする企業では、人件費の安い海外へ生産拠点を移す動きが本格化したのもこの頃でした。それに連動してか、国内では「リストラ」や「肩たたき」の動きがで始めたのです。
時代で言うと1980年代後半ごろからだったと思います。
これは奇しくもバブル景気の時期と重なるところがある訳ですが、好景気の陰で企業内では「リストラ」や「肩たたき」そして「希望退職」の動きが具体化され始めていたのです。
今回取り上げる「40代はもう若くはない?」という企業の若返り対策は「リストラ」、「肩たたき」、「希望退職」の動きとは内容的に完全に一致するものではありませんが、人員削減のプロローグと考えることができます。決定的な違いは社内告知されるかどうかです。「リストラ」などが社内全体に告知されるのに対し、わたしが問題にしている今回の「40代はもう若くはない」という企業の方針(考え方)は社内告知はされませんから、ある意味リストラ等より陰湿な手段と言えます。
「果たして今の時代も企業の考え方は変わっていないのか?」そして「40代前後は企業の中心として活躍するには無理があるのか?」など、いまの自分には直接関係ない事柄なのですが、考えてしまうことがしばしばあります。それは自分自身が、かつてそんな不遇の時代にアラフォーだったからだと思います。
個人的には、40代前後は羨ましいほどに若いと思っています。
しかし、果たして現代社会(会社の多く)はどう判断しているのでしょうか?
今の時代、企業はアラフォー世代をどうみているのか?
さて、新聞やテレビでこの種の状況を知ろうとしても、マスコミはこうした問題を取り上げることには消極的です。恐らく何か労基法などに絡む大事件でも起こらない限り、取り上げることはないでしょう。
仮に社会全体の傾向は読めたとしても、自分の会社の状況はやはり組織の一員として現役でいないと分からないものです。
退職して現役を離れた頃は「やれやれ、組織内の軋轢、重圧から解放された!」とか「人間関係のしがらみから解放された!」と喜び一辺倒だったのですが、組織内に所属していない現在は何も情報は入ってきません。完全に時代に取り残された状態です。
今のわたしは言わば「井の中の蛙」状態と言えます。
社会の一員でいるとは、まさしくこう言うことだったのかと気付かされます。
当時は、自分の職場は居心地が悪いと思っていましたが、組織の一員でいれば、それなりのメリットもあったのだと見直しました。
思いがけないところで、何とも言えぬ悲哀を味わってしまったもので、一人落ち込むことも。一般に、定年退職した人がその後の人生で、生き甲斐を見出せず無気力に陥ってしまうと言うことをよく聞きますが、よくわかる気がします。疎外感や漠然とした不安感に襲われるからでしょう。
かと言って、わたしは現在やりたいことが沢山あるので、今更組織人に戻りたいとは思いませんが。
さて、気を取り直して、「果たして今の時代はアラフォー世代はどうなのだろうか?」と考えてみます。
例えば、比較的大きな総合病院などでは、30代後半から40代初めと思しき若き医師が活躍しているのを多く見かけますが、社会全体としたら果たしてどうなのでしょうか。
 |
| Gerd AltmannによるPixabayからの画像 |
40代前後として自分は期待されているのかどうか。存在感はあるか薄いのか。
居心地は良いか悪いか。自分だけに風当たりが強いのかどうか、などなど。
さらに、会社の中心的業務を任されているかどうか。
この辺りがシンプルですが、自分なりの判断の手掛かりになると思います。
日ごろの職場でそうした雰囲気を肌で感じているかどうかだと思います。
人事異動、昇格昇給は学校での成績表
それに対し、人事異動、配置転換、昇給昇格などの結果内容は学校でいう成績表ですから、会社があなたをどのように評価しているかの意思表示でありバロメーターですから一目瞭然です。
所謂、査定です。人事考課なんて厳かな言葉もありますね。
皆さんも、人事異動の時期はソワソワしてその結果が気になり、仕事が手につかないといった経験があったと思います。
さて、わたしがここで問題にするのは、そうした制度自体についてではありません。
制度とは如何に行われているかが重要なのです。要するに「良い物も使い方を間違えると役に立たない」ということを言いたいのです。
例えば、人事異動というのは組織の活性化には必要不可欠な制度と言えます。ところが、その制度が悪用されると、「嫌がらせ人事」や「馴れ合い人事」といった、活性化とは真逆の結果を産むことになるのです。ですから、重要なのは会社の制度が不公平感なく健全に運用されているかに関心を向けることです。
 |
| Gerd AltmannによるPixabayからの画像 |
時代背景を考えることが重要
確かにわたしの時代は、アラフォー世代は露骨に年寄り扱い(邪魔者扱いとも言う)されました。振り返るに、当時は社会全体が不景気で企業の業績が以前のように右肩上がりに伸びなかったという時代背景がありました。これは冒頭で述べた通りです。
さらにもう一つは、新人を採用しなかったり、正社員の欠員をパート職員で補充したりと、経費の節減(言い換えれば人員削減)に企業は躍起だったということもありました。
こうした時代背景を踏まえた上で、「アラフォー世代は何故年寄り扱いされるのか?」の問題を考える必要があると思っています。
極論ですが、企業は業績が順調であれば、人減らしなどの人員削減策は考えないと言って良いと思います。要は業績がピンチのときに、手っ取り早い解決策として取るのが人員削減策なのですから。
わたしは経済のスペシャリストではないので、専門的なことは分かりませんが、当時と現在の社会情勢を比較したとき、不景気という面では似たような時代背景だったと思います。
ですから、いまの時代もアラフォー世代が人員削減のターゲットになっていると考えても不自然ではありません。
 |
| Gerd AltmannによるPixabayからの画像 |
余談ですが、最近は賃上げの機運が高まっているようで「ベースアップ率何%」と言ったお話をニュース等で聞きますが、それも大企業が中心の話で、中小企業や特にサービス業などでは相変わらずの低賃金での就労が続いているとのこと。
当時は「エッセンシャルワーカー」などといった洒落た名称はありませんでしたが、この人たちこそ最優先に優遇されるべきなのに改善されていないのが現状です。
そう考えると、ザックリとした捉え方かもしれませんが、弱い立場の人たちが不利という面では、当時と現在は極めて類似した社会情勢だと言えます。大企業以外の職場では、依然として人を減らす傾向は続いているとみるのが自然なように思います。
当時、わたしが勤めていた会社は同業他社に比べて遅れていたので、ライバルに追い付け追い越せと必死なところがありました。
そのため、業績を上げるためには、業績(売上など)を伸ばすよりも、経費を削減することの方が手っ取り早い手段として考えられ、後者が優先されました。
そして唐突に「スリム30(正式名称は不明)」という方策が提案され検討されました。この「スリム30」については別の機会に詳しく述べたいと思っていますが、要は名前の通り業務効率化のプログラムで、究極は合理化であり人員削減計画の一環だったのです。
「40代はもう若くはない」=「組織内の若返り運動」
このように、中小組織はあらゆる施策をこらして困難を乗り越えてきたのですが、あの時代、実はもうひとつ生き残り戦略として大きな社会の流れ(トレンド)があったのです。
それが今回取り上げる、「40代はもう若くはない」、いわゆる「組織内の若返り運動」です。
例えば、従来50代でようやく支店長(店長)になっていた企業内慣習を、40代でも抜擢するような人事制度の変更です。課長や係長もそれに応じて若返るというのがこの若返り運動の全体像です。
一見、良さそうな制度に思えるのですが、前述したように、ひとたび運用を間違えると制度は暴走します。
かつてのわたしの職場の例では、平職員などは「組織内の若返り運動」についてそれほど深く考えることなく、むしろ歓迎する職員も多かったように見受けられました。
実はこの若返り運動の延長線上にあったのが、かつての日本社会に蔓延した「モーレツ社員」や「24時間働けますか?」と言った現実離れした労働トレンドだった訳ですが、今回はそのことまでは触れられません。
実はこの「若返り運動」には資格職能制度というのがベースにあって、ある資格が無いといくら業務で頑張っても次のステップに進めないという構造になっていました。つまり、出世するには資格が必要ということで、今の時代なら当たり前のことだと思いますが、以前の日本社会では年功序列的に昇給昇格がなされていたので、当初は唐突過ぎて容易に馴染めなかったのです。
結果、若い世代は積極的に受験し資格を取ったのですが、アラフォー世代では抵抗感、あるいは諦念の境地に至った人もいたようです(わたしの元職場の場合)。
こうした分裂が後々「若返り運動」を進めるなかで弊害を産むことになります。
「若返り運動」の弊害とは
分裂の結果は、40代の職員の一部は出世街道まっしぐら、所謂、エリートコース入りです。
かたや資格のない職員は矜持を失い無気力、虚無感に陥り、精神を病んだ人もいました。
あるいは職場を去るという最悪の選択にまで発展したケースもあったのです。
 |
| DesignScape StudioによるPixabayからの画像 |
最終的にこの「若返り運動」は職員間の信頼関係を危うくし、職場はギスギスしました。要するに、今までの同僚が、もはや仲間ではなくて敵(ライバル)になったのですから。
さらに、上司にゴマをする職員が増えたことも大きな変化でした。
逆に、能力のある優秀な職員がいなくなる人材不足と言う皮肉な結果も招いたのです。
こうしたいくつかの事例が「若返り運動」の弊害だったのかも知れません。
『若返り運動』の犠牲者と窓際族とは違う
兎角、「窓際族」と呼ばれる人たちが話題になりますが、一般的にそう呼ばれるのは定年間近の年配者が多いと思います。
しかし、ここで言う「若返り運動」の犠牲者は30代から40代のまだまだこれからの人たちのことなのです。
これは全くの私見ですが、年配者の中には気の毒に思いますが、「窓際族」と揶揄されても致し方ない人たちが一定程度存在していたと感じています。わたしも高齢者の一人として考えたとき、当時も複雑な心境でしたが、業務に消極的な年配者がわたしの周りでもいたのです。
現に、職場にパソコンなどIT機器が導入され始めた頃、その操作方法を覚えることに消極的な上司が多かったことを改めて思い出します。
「もう若くはなくし、頭かたいから」とか「他の人にやってもらうから」などの言い訳を言って、積極的に覚えようとしない年配者、中間管理職、役席が多かったのです。
当時、わたしは操作を教える側にいたので、そのことはいまでも鮮明に覚えています。
 |
| Hafsa MoidunniによるPixabayからの画像 |
そんな我が社であっても、30代、40代の人たちは、まだまだ将来に向けての展望があったはずです。それを一定の物差し(年代という)で、いとも簡単にダメというレッテルを貼ったのでした。モチベーションが下がったのは当然です。
残念ながら、わたしも当時40代だったので、レッテルを貼られた一人だったようです。
人間は十人十色で、大成する時期はそれぞれ違うと思います。
一番の問題点は、個人一人ひとりを評価するのではなくて、30代、40代という年代で十把一絡げに判断するという当時の荒業です。
当時の企業側は一律に「40代はもう若くはない、発想が古い」「40代前後は将来に期待が持てない」「40代以上は企業にとって厄介者」といった見方をしていたのです。
社会全般が「40代はもう若くはない」という考え方で充満していたのです。
「組織の若返り運動」もその運用が重要
さて、この間「40代はもう若くはない」という視点で「組織の若返り運動」とその問題点を述べてきましたが、実は最大の問題点はその運用にあるのです。若返り運動の制度そのものは至って健全で優れた制度だと、わたしはいまでも信じています。正しく運用されれば誰にも公平な制度で、仕事にやり甲斐が持てる仕組みだと思っています。
健全な能力主義なら受け入れることはできたと思っています。
ところが、当該の「若返り運動」は残念なことに健全ではなかったのです。
経営側の「若返り運動」のセールスポイントは、簡潔に言えば「若い人たちの柔軟で豊かな発想力と行動力で組織を活気づける」です。
そのため、当然のこととして若い世代が期待されるのは然りです。しかし、「若い」という表現はいたって抽象的で曖昧です。むしろ、「柔軟で豊かな発想力と行動力で組織を活気づける」ことが可能な人こそ年齢に関係なく「若い」と定義した方が簡潔だと思うのですが・・・
その意味でしたら40代にも若い人(適任者)はいたはずです。
しかしながら、経営側がいう「若返り運動」はあくまでも建前であって、本音は「経費節減」「人員削減」にあったのでしょう。
 |
| Engin AkyurtによるPixabayからの画像 |
さて、「若い」という言葉の曖昧性を除けば、上記のセールスポイントは大義名分だと思います。
なので、「若い人を積極的に抜擢して活躍してもらう」は非常に理解できますが、その抜擢の仕方が依怙贔屓や人脈(派閥)によるものだったら話は別です。
例えば、特定のサークル(部)に入っていると昇格が早いといった妙な現象があることはよく聴く話です。わが社でも実際に多々あったようです。そのため、昇格の不公平感や将来に希望が持てないなどを理由に、退職していった職員も多かった訳です。
これでは「若返り運動」という折角の制度は台無しで、実態は「馴れ合い人事」という旧態依然のままということなります。
現代は「氷の世界」なのか?
改めて、皆さんの会社ではどうなのでしょうか?
40代前後の職員にアゲンストの風が吹いていませんか?
肉体の若返りを考えると、わたしの時代よりは現代の40代はまだまだできる世代だとわたしは信じています。
 |
| Azmi TalibによるPixabayからの画像 |
「優秀な人材は戦力である」は、新人向けのスピーチの常套句となっています。
その反面、依怙贔屓や人脈によって人事がなされているのも現実なのです。
そんな歪んだ職場では優秀な人材は育たないのも当然で、お偉方は過去の教訓としてこの点を深く反省すべきでしょう。
折しも、昨今のニュースによれば「退職代行会社」が繁盛しているとのこと。わたしの時代では想像すらできなかった業種であり、今の社会にあって一定程度のニーズがあるというのですから驚きです。わたしの時代は会社を退職する(辞める)ということは一大決心だったのですが、最近ではいとも簡単に辞める決断ができるのは単に「時代の趨勢」と片付けて良いものなのでしょうか。これほどまでに社員と企業の信頼関係は薄れたのかと、このニュースを聞き寂しさを飛び越えて危機感すら覚えました。
およそ半世紀前、井上陽水が「氷の世界」というアルバムをだしました。そのアルバムタイトルにもなった「氷の世界」という曲は、歌詞がとてもシュールで難解なため、如何ようにも解釈ができるのですが、この投稿を書いていてわたしは、現代という時代は陽水が謳う「氷の世界」そのものに思えました。機会があったら、皆さんもこの曲の特に歌詞に注目して聴いていただけたらと思います。
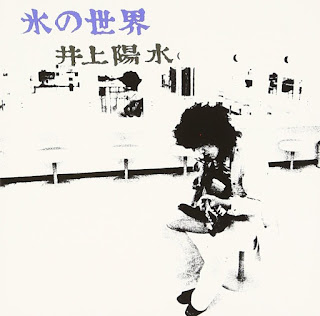 |
| 井上陽水 アルバム「氷の世界」 |
厳しい時代、生き残り戦略の中で企業は、かつてわたしが所属した会社のように、勇み足で自社の優秀な人材を失わないようにご注意ください。
その昔、企業は定年退職による欠員を、新入職員や中途職員採用などで補充し、職員の数を徐々に増やしていきました。高度経済成長の時は人員はピークとなり、やがて、機械化や諸々の事情で企業は人員を減らす方向へ転換していったのです。
今回取り上げた「アラフォー世代は何故に年寄り扱いされるのか?」はそんな時代の流れの中から必然的に出た現象だと思っています。
「リストラ」や「肩たたき」ほどダイレクトではありませんが、漠然と退職を促す手法は実に巧妙でした。そして「リストラ」や「肩たたき」といった企業の合理化につながっていったのです。
もはや、AIが注目され、「無人***」といった商品などが次々と開発されている昨今、時代の後戻りは望めないでしょうから、企業の人減らし政策はますますエスカレートするばかりだと思います。そして次にやって来るのは、若い人への「もう君はいらないよ」という一言かも知れません。
最後に
この投稿を書きつつ感じたことですが、最近のニュース等での「ある表現」に違和感を感じたので記しておきます。それはAIなどの技術進歩で無人化の動きが加速化しているといった内容のニュースに対してです。そのニュースのなかで、AI化の理由として異口同音に揚がるのが「人員不足」という理由だったのです。そもそも人員不足の原因は企業が人を募集しないからで、企業の都合な訳です。
あたかも「職員募集をしても人が集まらない」的なニュアンスに聞こえますが、実態はそうではないはずです。
本当に人員不足なのはAI化にはあまり馴染まない、エッセンシャルワーカーと呼ばれる人たちが働く業種のはずです。恐らく、ニュース等放送では「人減らしのためにAIを導入」とは言えないので、仕方なく「人員不足」という安易な言葉で済ませたのかも知れません。
電車や車の運転を無人化する(一部では既に実施済みですが)大組織の発想が、そもそも的外れで人間を軽視している現れだと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この投稿が、組織内でひたむきに励む現役職員の方々への細やかな励みとなっていただければ幸いです。
from JDA
<追記>
本文が思いのほかロングバージョンになってしまったため、触れられなかったことがあります。それは「若返り運動」が上手く機能しなかった最大の原因についてです。
その原因は、企業側が理想論に走りすぎ、実を伴っていなかったからだと思っています。
それはジョブローテーションが十分行われないままに、若返りを急いだことです。業務経験、人生経験もないままに役職についても、それに敵った職務を全うできる訳がないからです。
その意味では、当時のエリート職員として抜擢された方々も、さぞやご苦労されたことと思います。

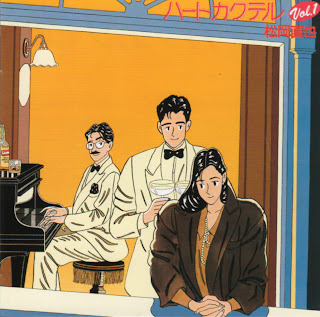

コメント
コメントを投稿