田中一村 展 <不屈の情熱の軌跡>を観て感じたこと
今年の9月19日から開催された「田中一村 展」も昨日の12月1日が最終日でした。
マスコミ等の報道をみると、連日盛況だったようです。
それもそのはず、展示会開催期間中にもNHKをはじめテレビ等でも田中一村に関する番組が急遽、複数も組まれるという反響ぶりだったのですから。
展示会の開催前から、確かに「田中一村 展」はかなり話題で注目されていた訳ですが、それ以上の主催者の意図を上回る盛況ぶりだったはずです。
わたしも熱狂ぶりがほとぼり冷めたころを狙い、開催から3週間ほどして訪れたのですが、それでも混雑ぶりは大変なものでしたから。
🔷
改めて、去る10月10日(木)、「田中一村 展」を観に上野の東京都美術館へ行ってきました。
実際に観に行ってからこの投稿までにかなりの日数がかかったのは、わたし自身の実生活がドタバタしていたことと、怠慢(?)によるものと反省しております。
そのため、どうせ遅れるのなら展示会の終了に合わせての投稿にしようと思った次第です。
 |
| 東京都美術館正面入り口 |
10月に入っても、一向に秋らしい晴天に恵まれない昨今でしたが、当日は曇り空とは言えマズマズの天候。週間天気予報によれば次の11日が快晴とあり、混雑が予想されるのでその日を避けて10日としたのですが、思惑とは裏腹に美術館は大混雑でした。
田中一村がここまで人気だとは、どうやらわたしの考えが甘かったようです。
 |
| フェルメール <真珠の耳飾りの少女> |
この間、上野公園には何度も訪れていたので、そこまでご無沙汰とは思っていませんでした。
このときの一番の注目作品がフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」でした。
そのため、このときも会場は連日大混雑で、「真珠の耳飾りの少女」の部屋では入場制限が出たように記憶しています。
 |
| 東京芸大へ向かう途中にある上島珈琲店 |
そう、この頃から美術館を訪れる人たちが俄かに増え始めたように感じました。
わたしが学生の頃(半世紀ほど前!?)は、ゴッホや印象派の展覧会でなければ、優雅に鑑賞できるほど会場は空いていたのですが、テレビ局や新聞社などが主催、協賛し始めてからは美術館の来客動員数はグンと増えたと物の本に書いてありました。こうした状況が良いのか悪いのかは人それぞれの判断ですが、このことについては以前、別の投稿「プーシキン美術館展 フランス絵画300年 個人のマナーと開催運営に問題あり」で触れているのでよろしければそちらを参照してください。
*プーシキン美術館展 フランス絵画300年 個人のマナーと開催運営に問題あり
さて、今回の「田中一村 展」に話を戻します。
 |
| 田中一村展パンフ 表面 |
会場にあった作品一覧資料によると311作品とのこと。
この数を他の展示会とくらべてみると、一個人の展示会としては圧倒的な数です。
展示は大きく時系列に3章に分かれ、次のように部屋分けされていました。
- 第1章 若き南画家「田中米邨」東京時代 74作品
- 第2章 千葉時代「一村」誕生 130作品
- 第3章 己の道 奄美へ 107作品
しかしながら、その中央画壇への絶望が奄美へと導き、あの「一村の画風」を確立し今日の栄光があるのですから、人生は皮肉としか言いようがありません。
それは彼が中央画壇への出展の際に、当時の東京美術学校のライバルたちが大成して審査員の立場にいたこと、さらには作品が評価されなかったことを思えば、このときの「一村の心境や如何に」だと思わずにはいられません。
わたしたちは日々を一生懸命過ごしていると、誰にでも大なり小なりこうした不条理な経験に遭遇するはずです。
例えば「自分は一生懸命頑張っているのに、誰も評価してくれない」とか「正直ものはバカを見る」といった心境になったときです。
会場をあとにした時、わたしがまず思ったのがそのことでした。
帰りに上野精養軒の名物(?)ランチ「パンダプレート」を家内と二人で食べて帰りました。
帰路の電車にゆられながら、田中一村の現在の反響が一時的なブームに終わらないことを願いつつ、久しぶりの長距離歩行による程よい筋肉痛を楽しみながらの帰宅でした。
昨今、幸か不幸か美術展の来客数が増加傾向にあるように感じています。芸術を愛する一員として混雑した中での鑑賞は集中できませんし、そもそも芸術鑑賞の環境ではないと感じます。





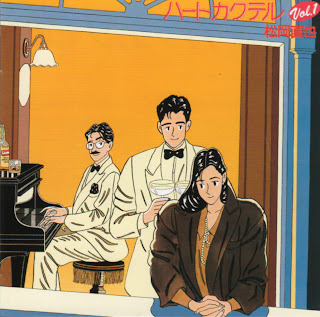

コメント
コメントを投稿