バキュームカーがやって来た
わたしは断片的ですが、3歳ぐらいの出来事をいくつか覚えています。
身近な人に尋ねてみると、それはかなり凄いことらしいのですが、そんな記憶の統計はどこにもないでしょうから、自分としては何とも言えません。
 |
| Xuan DuongによるPixabayからの画像 |
しかしながら、3歳よりは遥かに後の出来事と思われる、ある事に関しての記憶がまったく無いことに最近気が付いたのです。そのある事とは極めてバカらしい事柄なのですが、「自分の実家のトイレはいつ頃水洗トイレになったのか?」という疑問です。先日トイレに入っていた時に、そんなどうでもよい疑問が何気なく頭をよぎったのです。
そんな訳で、今回は昭和の香りが漂うチョッとテレ臭いお話です。
🔷
調べてみると、日本では意外にはやく、関東大震災の後に下水道、浄化槽の整備が本格的に進められ、それに並行して水洗トイレは出始めたそうです。
とは言え、一般の家庭に普及するのはまだまだ先のことだったようですが。
ご承知の通り1960年代に入ると、日本は高度経済成長の時代に入り、その豊かさの表れのひとつが水洗トイレだったのかも知れません。そして日本住宅公団の団地建設を機に、一般家庭にも徐々に普及し始めたそうです。
そんな概要がわかってくると、トイレに関する自分の記憶も少しづつ鮮明になってきました。
そう!思い起こせば、わが両親が待望のマイホームを横浜の本牧近隣に建てたのが、
1950年代後半の頃で、そのときのトイレは確かに、世に言う「ぼっとんトイレ」だったのを覚えています。それから数年して水洗トイレに改装されたはずです。まさに昭和で言えば、30年代の中期から後期にかけてのことだったと思います。
ですから、当時のわが家にとってはトイレ改装は画期的な出来事だったと思うのですが、わたしはその当時の状況をまったく思い出せなかったと言うか、そんなことさえ最近まで考えたことが無かったのです。
テレビがわか家にやってきたときは、学校の授業も上の空でワクワクだった自分を昨日の事のように覚えているのに、水洗トイレの件はインパクトゼロだった訳です。
そもそも、子供はテレビや自転車など遊びに関係することには夢中でも、水洗トイレのことなんて、どうでもよかったのでしょう。
トイレなんてできるだけ居たくない場所ですから、記憶の圏外なのは当然かも知れません。
さて、記憶とは不思議なもので、水洗トイレについてググっていたら、トイレにまつわる思い出が次々と蘇ってきました。
こんなくだらない話をブログに投稿するのは、相応しいのかどうか迷いましたが、逆にみんなが避ける話題なら、昭和の一つの記録として残そうと思い投稿しました。
巷では、今年(2025年)が昭和で言えば100年に該当、という節目の年でもありますから。
実は、「バキュームカーがやって来た」のタイトルで投稿するには、もう一つ別の理由があるのですが、それは最後にお話します。
では、そんなニオイ(?)のするお話をひとつふたつご紹介しましょう。
いまの若い人たちには想像もつかないことかもしれませんが、1960年前後、和暦で言えば昭和35年前後の時代は、前述した通り「ぼっとんトイレ」、いわゆる「汲み取り式トイレ」がまだまだ主流でした。
ですから、ドリフターズのカト茶さんが「8時だよ、全員集合!」のテレビの中で扮していた、天秤棒の両端に樽を下げた「汲み取りおじさん」が、あの頃はそれぞれの地域に必ずいたのです。
いま思えば、社会にとって必要不可欠で大変重要な仕事だったにも拘らず、周囲の目(わが家も含め)は、彼らを若干蔑むような傾向にあったように思います。
そもそも、あのおじさんたちの身分というか職業というか、誰に雇われているかさえも何も分からないのですから。ただ、家は近所だったように思います。
いまになって思えば、感謝しなければいけない人に、私たちは大変に失礼なことをしていた訳です。
思えば、むかしは現代よりも前述のような職業、いまで言うエッセンシャルワーカーの人たちや身障者、ホームレスなどに対して冷ややかだったり、無神経だったように思います。
いまでも、ヘイトスピーチなど一部にはそうした攻撃的な傾向は見受けられますが、むかしは社会全般にそんな雰囲気があったように思います。
それから較べると、彼らに向けての呼称だけでも改められたことは前進なのでしょうが、身分保障などで足りない面もあり残念に思います。
🔷
話をトイレに戻しますと、時代が進み汚水処理は「人力」から「バキュームカー」の時代へと推移します。とは言え一軒一軒個別に回ることには変わりはないのですが。
その頃、小学校低学年だったわたしたちは、バキュームカーから大蛇のように延びたゴムホースがブルブルと振動するのを見ては、ゲラゲラ笑い、鼻を摘まみながら「臭い!」と叫んで、その場を立ち去ったものでした。
バキュームカーのおじさん(恐らく市の職員)も、言われるままではなくて、「誰から出たと思ってんだー!」と応戦するのですが、子供は「何処吹く風」です。
子供とはストレートで、何と残酷なのでしょうか。
いま思い出すと、冷や汗もので、只々反省あるのみですが、救われるのは当時のおじさんの表情と声には、どこか笑みが感じられたことです。
そんなやり取りには、いまの時代にみる陰湿さはなくて、どこかおおらかでホノボノとした暖かさすら感じます。(当時は逃げるのに必死でしたが・・・)
 |
| Tomasz MarciniakによるPixabayからの画像 |
当時は近所の子供を平気で叱ったりする「恐いおじさん」が、地域には一人や二人はいたものです。それでも、何の問題もなかった時代だったんです。
そうしたおじさんたちはある意味「憎まれ役」だった訳ですが、それで地域の治安が保たれていたということも、あったのかも知れません。
🔷
懐かしくて、あの時代に戻りたいと思っても、時はゆっくりと、でも確実に変化して現在に至ったのですから、逆行するのは所詮無理な話です。振り返れば、人間社会のしきたりや慣例というのは、すこしの変化と長年の積み重ねで大きく様変わりし、いまに至っているのです。
ですから、昔のやり方が通用しないのは寧ろ当然なことなのです。
こうした現象は例えるなら、競技場などで自然発生的にできた観客のウェーブのようなものだと思います。ひとたび起きてしまうと一人の力ではどうしようもなく逆らえない状況と同じです。そんな巨大なウェーブの中に、わたしたち昭和の中高年は吞み込まれたようなものです。
ウェーブを構成する一員に成れないままに。
特に最近では、そうした世の中の変化が一昔前にくらべて物凄くスピードアップしていますから、尚更辛いです。そうなると、わたしたちは只々傍観するしかないのです。
きっと、あの当時のおじさんたちも、いまのわたしたちと同様に、新世代の若者たちを同じような目で見ていたのかも知れまさん。さぞ寂しい思いだったと推察されます。
 |
| Yazril Tri MulyanaによるPixabayからの画像 |
最近は、昭和の時代、それも自分が「子供の頃の昭和はよかったなー!」と思うことがよくあります。パソコンもインターネットもゲームもなかった時代、あったのはラジオとテレビと自転車ぐらいだったけれど、笑顔も会話も希望も今よりズッとたくさんあったように思います。
そんなかつての時代が懐かしく羨ましく思えるのは、その時代には決して戻れないことを、私たちはわかっているからなのでしょう。
駐留する米軍がいて、まだまだ戦後の傷跡が残っていたあの昭和の時代、バキュームカーはボクらの笑いのネタだったけど、ある意味、希望や進歩の象徴だったのかもしれません。
水洗トイレがあり、ウォシュレットがあり、清潔感にあふれている現代社会は、彼らの苦労の上に成り立っていることを、決して忘れてはならないと思います。
なにげない日々の中で、ふと甦るかつての苦い思い出の中には、ときに後ろめたさで胸がイッパイになってしまうことがあります。そんなときは、今回のように思い切り吐き出すのが一番だと思っています。
人生も晩年(?)にさしかかると、懺悔的なことが多くなります(-_-メ)
実は、前段で触れた今回の投稿に至るもう一つの理由はここにあったのです。
この場を借りまして、当時、人の嫌がる仕事を黙々とこなしていた天秤棒のおじさんや、バキュームカーのおじさんたちに遅ればせながら、心からの敬意を表したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
from JDA
<追記>
今回、チョッとした水洗トイレの話題が、トイレの歴史にまで発展してしまいました。
とは言え、書き終えた後も、思い出される事柄が次々と出てきまして、例えば、現在のような「座る水洗トイレ」の前は「またぐ水洗便器」などもあって、小学校、中学校などではこれが一般的でしたネ。そんなこともすっかり忘れていました。


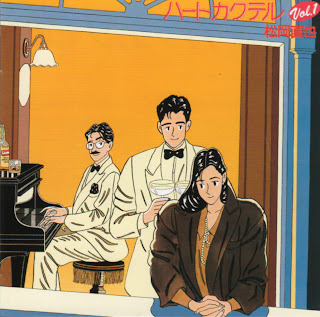

コメント
コメントを投稿