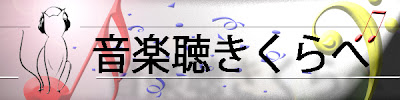ジャケ買い天国: シリーズ第2弾 ビル・エバンス&ジム・ホール「Undercurrent」

ビル・エバンス&ジム・ホール 「アンダーカレント」 Bill Evans & Jim Hall 「Undercurrent」 おもて面に何もロゴがないのは 最近のアルバムではよく見かけるが、 この当時としては非常に意欲的な試み。 1 My Funny Valentine 5:23 2 I Hear A Rhapsody 4:38 3 Dream Gypsy 4:33 4 Romain 5:21 5 Skating In Central Park 5:20 6 Darn That Dream 5:08 ビル・エバンス(P) ジム・ホール(G) 1962年4月24日、5月14日録音 iTunes Storeで試聴できます。 前回のマドンナ「ライク・ア・ヴァージン」に引き続き、今回もモノクロ的アルバムである。 モノクロ写真の時代にカラー写真が出現し、そのカラー写真が当り前になると逆にモノクロ写真に新鮮さを感じるというこうした複雑な感覚は、果たして人間だけに備わったものなのだろうか。ある意味、何とも移り気で我儘で欲深だと思うのだが、結局それでこそ人間なのかも知れない。 と言うか、そもそも動物の世界はモノクロと聞いたことがあるのだが... 冗談はさて置き、強烈なインパクトを期待するならカラーよりモノクロと言うのが今の定番。 このアルバムが発売された当時は、モノクロ感覚は至って斬新でユニークな印象だったはずで、前述した人間の色に対する複雑な感覚が認識され始めた頃だったのだろう。 モノクロジャケットに加え、ジャケットのおもて面にタイトルやアーチスト名を一切入れない試みも、当時としては画期的なことで体制に背く異端的立場を強く主張しているかのようだ。 思えばこのアルバム、何から何まで当時の常識を覆す革新的要素が詰まったアルバムだと思う。キャッチコピーも説明もないが、それ故に見る者に無言の訴えを...